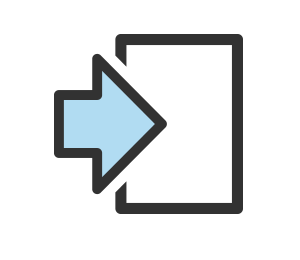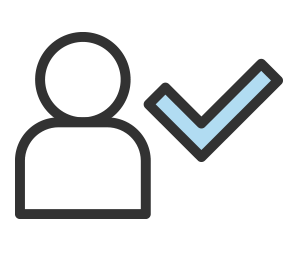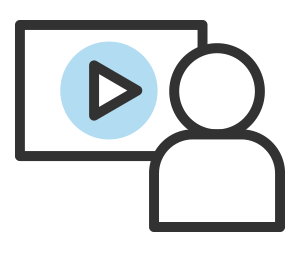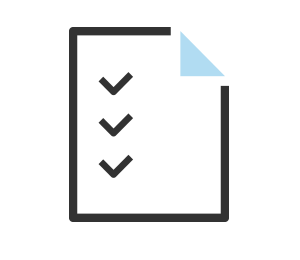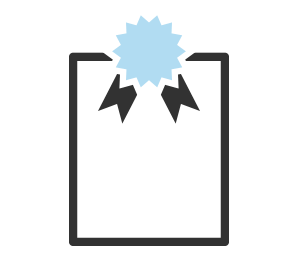2021年度第5回
2022年3月22日(火)17:30-19:30
中学校技術・家庭科 D情報の技術におけるプログラミングの指導
Society5.0の実現を目指す教育改革として、学校におけるプログラミング教育が注目されています。
中学校では、技術・家庭科技術分野(技術科)においてプログラミング教育が行われています。
しかし、新設されたD(2)「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」は、これまでの実践事例の蓄積がなく、多くの先生方が授業づくりに困り感をもっています。
そこでJMOOCでは、対応するオンライン講座を開講しました。本ワークショップでは、各講座の担当者により、各講座の内容紹介を行います。
https://www.jmooc.jp/workshop20220322/
講演1講師:森山 潤(兵庫教育教育大学・教授)
講演2講師:森山 潤(兵庫教育大学大学院 教授)、宮川 洋一(岩手大学教育学部 教授)、渡津 光司(東京学芸大学附属国際中等教育学校 教諭)、
川路 智治(茨城大学教育学部 助教)、
尾﨑 誠(厚木市立荻野中学校 総括教諭)、吉田 拓也(東大寺学園中学校・高等学校 教諭)、
三浦 寿史(熊本大学教育学部附属中学校 教諭)、
磯部 征尊(愛知教育大学教育学部 准教授)
講演3講師:上野 耕史(文部科学省 初等中等教育局 視学官)
このワークショップを初めから観る
2021年度第4回
2022年1月31日(月) 18:30-20:00
教育DXをGIGAスクールから学ぶ ~GIGAスクール導入をどのように課題解決してきたか~
コロナ禍のインパクトは教育にどのような変容をもたらしているのでしょうか。
高等教育ではオンライン授業に焦点が当てられますが、初中等教育ではGIGA(Global and Innovation Gateway for All)スクール構想を2年前倒し実施した結果、大学どころではない大規模な変動をもたらしています。
GIGAスクール実施の現場の混乱と工夫、そこから得られる教育DX(Digital Transformation)へのヒントを参加者と話し合うワークショップを企画しました。
https://www.jmooc.jp/workshop20220131/
講演1講師:豊福晋平(国際大学GLOCOM)
講演2講師:平井 聡一郎(情報通信総合研究所)
このワークショップを初めから観る
2021年度第3回
11月13日(土)17:00-18:30
eラーニングアワード2021フォーラム内
JMOOCが提供するAI・データサイエンスMOOC講座の展開と展望
このMOOC講座は、日本を代表するAI専門家及びそれを活用している実務家によるAI・データサイエンス学習の決定版です。AIをビジネスに活かす経営層からマネージャー層、そしてAIを実装する現場層まで学べる充実した内容で、2021年6月30日の開講以来、3ヶ月で1万人の受講者に達しています。今後の教育事業としてのオンライン講座への展開と展望を語り合いましょう。
https://www.jmooc.jp/workshop20211113/
講演1講師:安浦寛人(国立情報学研究所特任教授 )
講演2講師:佐々木基弘((株)ドコモgacco代表取締役社長CEO)
このワークショップを初めから観る
2021年度第2回
2021年9月21日(火)13:30-15:15
海外大学と連携した授業実施とその基礎技術
我が国の大学の海外展開、海外の大学の国内展開など、今や教育は国境を超えるようになってきています。また、このような教育を支援するソフトウェアの幅も広がってきています。しかし、そのノウハウは教員の間で共有されているとは言い難い状態です。
本ワークショップでは、海外大学と連携した教育を行う時のノウハウの共有を目指して企画いたしました。
https://www.jmooc.jp/workshop20210921/
講演1講師:井上 雅裕(慶應義塾大学大学院システムデザイン・ マネジメント研究科・特任教授、日本工学教育協会・理事)
講演2講師:芦沢 真五(東洋大学、前UMAP国際事務局事務次長)
講演3講師:石崎 浩之(芝浦工業大学客員教授、マレーシアオフィス所長、Asia Technological University Network (ATU-Net)モビリティ小委員会チェア)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年8月29日(土)15:30-17:30
テーマ4.大学の国際化の新展開とリスク管理
IT人材獲得と育成のグローバリズム
我が国におけるIT人材不足は,30年以上前から,経済産業省(当時は通商産業省)や総務省等に指摘され続けてきた大問題でありながら,一度も解消・解決されたことがありません。2019年に経産省が発表した試算では,2030年には約79万人が不足するとされています。新型コロナウィルス感染症拡大の影響により,テレワーク,eラーニング,WEB面接,遠隔診療など,ITのフル活用無しには明るい未来が望めない昨今の状況を鑑みても,人類社会全体のデジタル化の加速を担える優れた人材を獲得し育成することは,より一層の急務と言えます。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-13/
趣旨説明:長谷川亘(一般社団法人日本IT団体連盟代表理事・筆頭副会長 )
講演1講師:寺下陽一(京都情報大学院大学 副学長)
講演2講師:吉江修(早稲田大学大学院情報生産システム研究科 教授 )
講演3講師:Ahmed El-Gohary(エジプト日本科学技術大学(E-JUST)学長 )、後藤敏(エジプト日本科学技術大学(E-JUST)副学長)
講演4講師:長 小暮(株式会社エム・ソフト 取締役会長)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年8月8日(土) 20:00-22:00
テーマ4.大学の国際化の新展開とリスク管理
海外大学のオンライン教育の取り組みとそこから学べる教訓
新型コロナウィルス感染拡大は、高等教育機関においてオンラインによる授業配信を行わざる得ない状況をつくりだしました。オンラインによる授業配信など今回の困難な状況を克服するためにその利用が拡大した教育手段は、コロナ禍が収まった状況下でも教育の質と量を確保するために継続して利用されるであろうことが7月4日の「大学の国際化の新展開とリスク管理」シリーズの第1弾ワークショップ(https://www.jmooc.jp/workshop2020-6/)で日本の事例から確認できました。
本ワークショップでは、オンラインによる授業配信などがもたらす新たな大学教育・研究活動への貢献の可能性について、アジア・欧州・米国の試みを学ぶ中で議論をしたいと思います。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-11/
モデレーター:弦間正彦(早稲田大学国際担当理事)
講師:Dr. Suk-Ying Wong(Professor and Associate Vice President, Chinese University of Hong Kong)、Dr. Frances McCall Rosenbluth( Professor and Former Deputy Provost for Social Sciences, and for Faculty Development and Diversity, Yale University)、Dr. Piet Desmet(Professor and Vice Rector of Education, KU Leuven)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年7月4日(土) 10:00-12:00
テーマ4.大学の国際化の新展開とリスク管理
ポストコロナ禍時代の大学教育
新型コロナウィルス感染拡大は、高等教育機関においてオンラインによる授業配信を行わざる得ない状況をつくりだしました。困難な状況を克服するために新たな取り組みは継続して行われてきており、今後も新型コロナウィルス感染のリスクに継続して向きあう中で、教育の量と質を確保する努力が必要となっています。
本ワークショップでは、目標に掲げる大学教育を提供するために必要な方策を、ポストコロナ禍時代について議論します。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-6/
モデレーター:弦間正彦(早稲田大学国際担当理事)
基調講演1講師 :鈴木典比古(国際教養大学学長)
基調講演2講師:田中愛治(早稲田大学総長)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年6月20日(土)15:30-17:20
テーマ3.初等中等教育のICT化
初等中等教育を取り巻くICT環境
コロナ禍の中、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校では授業を行うことが出来ずに、家庭学習を余儀なくされました。一部の学校ではオンライン授業が実施されましたが、実践した学校は全国の5%程度だったとの報告もあります。その背景には、ICT環境の整備の課題があるとも言われています。その一方、GIGAスクール構想により、一人1台端末と高速大容量の通信ネットワークの一体的整備が加速しています。このワークショップでは初中等教育における、オンライン授業、GIGAスクール構想実現のために何をすべきかなどについて考えていきます。
今回のJMOOCワークショップでは、初等中等教育を取り巻くICTの今について、解説するとともに、高等教育への連携など初等中等教育を取り巻く教育について、考えます。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-4/
趣旨説明:中川一史(放送大学教授)
講演1講師:佐和伸明(千葉県柏市立手賀東小学校校長)
講演2講師:青木久美子(放送大学教授)
講演3講師:辰己丈夫(放送大学教授)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年8月18日(火)13:30-16:40
テーマ2.e-ラーニングの進歩
ポストコロナ時代に問われる授業用コンテンツの共有とeラーニングの進化
新型コロナ禍の影響により、『必要に迫られやむを得ず』急速にオンライン教育が推進されました。その結果、オンライン教育の効果、教育の質の維持・評価・保証、受講生のモチベーション、受講の継続、教育の効率などの本来課題が浮かび上がっています。本イベントでは、ポストコロナ時代を見据え、このような本来課題の解決を支えるテクノロジーを模索していきます。
「e-ラーニングの進歩」シリーズ3回目の今回は、教育にすぐに活用できる具体的な<教材コンテンツ>を見ていきます。それぞれの教育テーマで実際に商品化しているベンダーを招き、講演だけでなく、デモンストレーション、オンライン相談ができる場を提供することで、実質的に役立つ情報を得る事ができるイベントを目指します。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-12/
基調講演講師:加藤 憲治(特定非営利活動法人日本イーラーニングコンソシアム会長)
講演1講師:鷲崎 弘宜(早稲田大学教授)、鄭 顕志(早稲田大学理工学術院国際理工学センター 准教授)
講演2講師:細野 康男(デジタルハリウッド株式会社まなびメディア事業部プロデューサー)
講演3講師:桐原 憲昭((株)アイデミー事業本部エンタープライズサービス部長、筑波大学大学院 リスク工学専攻 非常勤講師)
講演4講師:栗山 健 (JMOOC理事・事務局長)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年6月30日(火)13:30-16:30
テーマ2.e-ラーニングの進歩
ポストコロナ時代のeラーニングシステムの在り方:デジタルエコシステム・相互運用性・IMS技術標準
新型コロナウイルスの緊急事態宣言下による学校閉鎖で、学生・児童・生徒は学ぶ機会を失いました。「誰一人取り残すことなく」学業を取り戻すために、多様な学びに対してそれぞれ最適な学びを実現するeラーニングには大きな可能性があります。
今回のオンラインワークショップは、学校での正規教育とノンフォーマル学習(タブレット等での家庭学習)、さらに学習塾やボランティアによる地域でのインフォーマル教育も連携させて、日々の学業の進捗を把握し、効果的・効率的な学びを実現するにはどうすればよいかを考えます。
また、教育の「ニューノーマル」について、学校や教員の負担を軽減しながら、より高品質な教材や授業を実現するためのソリューションとして、相互運用性のあるシステムやツールの連携可能性の実践例を紹介するとともに、ステークホルダー間の連携の可能性についても議論します。教育ツールの連携、教育コンテンツの共有、RPA(Robotic process Automation、事務作業の自動化)、データ主体(学習者や家庭)も参加する学修記録(スタディログ)の安全安心な管理と利活用、実用化されつつあるデジタルバッジによるマイクロクレデンシャルなどもご紹介する予定です。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-5/
第1部講師:山田恒夫(放送大学教授/(一社)日本IMS協会理事)、深澤良彰(NPO実務能力認定機構理事長)、川原洋((株)サイバー大学代表取締役・学長/(一社)日本IMS協会理事)
第2部講師:山田恒夫(放送大学教授/(一社)日本IMS協会理事)、北川光雄((株)ネットラーニング執行役員 オープンバッジ事業部長)、秦隆博((株)デジタル・ナレッジ 教育研究所 シニア・フェロー)、高橋恒樹((株)ソニー・グローバルエデュケーション 中長期企画部 ブロックチェーンプロジェクトリ)、圷 健太 (LasTrust(株) CEO)
第3部講師:常盤祐司((一社)日本IMS協会技術委員長)、畠山久(法政大学情報メディア教育研究センター講師)、常盤祐司(Fun@Learn代表/(一社)日本IMS協会技術委員長)、藤原茂雄((株)内田洋行 / 日本IMS協会 事務局長)
このワークショップを初めから観る