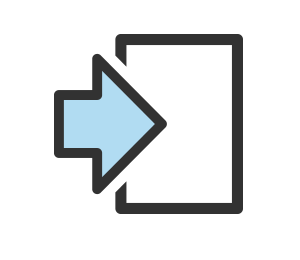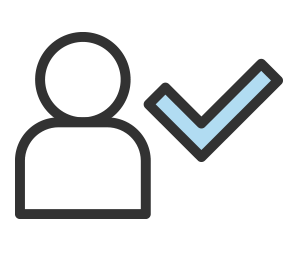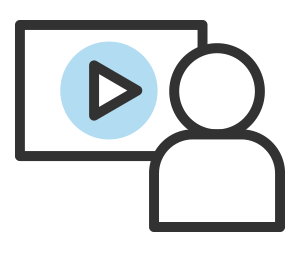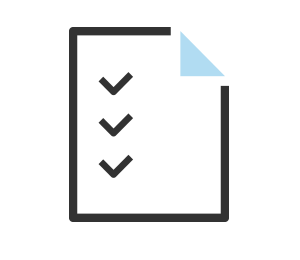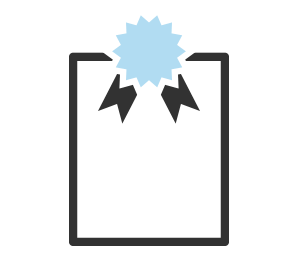2020年度
2020年6月9日(火)13:30-16:30
テーマ2.e-ラーニングの進歩
今、求められる新たな学び ~ポストコロナ時代の教育プラットフォーム~
コロナ禍により、教育機関は、急速にそして強制的にオンラインでの教育提供に舵を切りました。現状は、緊急避難的に対応しているという現状が多いのではないでしょうか。コロナ禍が収束したポストコロナの時代においても、このオンラインでの教育提供が一定程度維持された教育活動が想定されます。そして、緊急避難時期を過ぎたポストコロナ時代では、教育の質の維持・評価・保証、受講生のモチベーション、受講の継続、教員の効率など様々な本来課題を解決したオンラインでの教育提供とならなければなりません。
今回のJMOOC ワークショップでは、ポストコロナ時代を見据え、このような本来課題の解決を支えるテクノロジーやツールを模索するために議論いたします。実際に商品化しているベンダーを招き、セミナーやデモンストレーション、オンライン個別相談ができる場を提供することで、教育現場に実質的に役立つことを目指しています。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-2/
講演I講師:中嶋竜一((株)デジタル・ナレッジ)
講演II講師: 川原洋((株)サイバー大学代表取締役・学長/(一社)日本IMS協会理事)
講演III講師:岸田努(株式会社ネットラーニング代表取締役副社長/JMOOC理事)
講演IV講師:松崎剛(株式会社イーラーニング代表取締役社長/マイクロラーニングコンソーシアム理事)
講演Ⅴ講師: 田村信吾(シスコシステムズ合同会社 公共事業 事業推進本部 担当部長)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年8月1日(土)13:30-15:30
テーマ1.ネットワーク授業と新しい大学
応急措置のリモート授業から質の高いオンライン教育へ~学習者中心モデルを目指して~
コロナ禍の影響で、様々なレベルの教育機関で急遽応急措置的にリモート授業が行われました。長期的な計画に則って行われたものではなく、急遽必要に迫られて実施されたものがほとんどであるため、現場の様々な工夫が見られました。今後は、ウィズコロナ、及びポストコロナの時代の教育として、今回の経験を機に、長期的な展望に立って教育体制そのものを見直すことが必要となってきます。それは、コロナ禍以前から議論されてきたことでもありますが、今こそ真剣に考える時期に差し迫ってきているといえます。日本のオンライン教育は欧米の先進国に比べると数年遅れていると言われています。技術大国の日本ですが、大量生産時代の知識伝達型の教育方法が未だ主流です。未来の社会で自己実現を可能とする教育は、学習者の視点に立って設計されなければいけません。
今回のJMOOCワークショップでは、質の高いオンライン教育を目指すために、教育の質とはどういうことを意味するのか、質の高い教育を妨げる壁は何なのかを考え、日本の教育が世界に取り残されないように何をすればよいのかを、日本在住の外国人教員の視点も交えて考察します。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-10/
講演1講師:青木久美子(放送大学教授)
講演2講師:宮下 洋(東京都立昭和高等学校教諭)
パネルディスカッション登壇者:Nathan Curtis Gildart(名古屋国際学院教諭)、
José Domingo Cruz(北九州市立大学講師)、David Joseph Juteau(桜美林大学講師)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年7月25日(土)13:30-16:00
テーマ1.ネットワーク授業と新しい大学
成績評価と学習データの活用
新型コロナウイルス感染症の世界的拡散に対する教育継続の対策として、多くの大学でオンライン授業が一気呵成に導入されました。このような条件下でも、教育の質の維持・評価・保証、学生のモチベーションの継続、教員の効率化など様々な本質的課題を解決する必要があります。
今回のJMOOC ワークショップでは、コロナ禍における成績評価をどのように考えればよいのか、どのような手法が存在するのか、そして、それらの基となる学習データをどのように活用していくべきなのかについての講演の後、パネル討論により、論点を明確にしていきます。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-9/
講演1講師:重田 勝介(JMOOC理事/北海道大学情報基盤センター准教授・高等教育推進機構/オープンエデュケーションセンター副センター長)
講演2講師:緒方 広明(京都大学学術情報メディアセンター教授)
講演3講師:島田 敬士(九州大学大学院システム)
パネリスト:重田 勝介、緒方 広明、島田 敬士
コーディネータ:安浦 寛人(JMOOC副理事長/九州大学理事・副学長)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年7月4日(土) 15:30-17:30
テーマ1.ネットワーク授業と新しい大学
アクティブラーニングをオンライン授業で!
「オンライン授業をやるだけで手一杯なのに、オンラインでアクティブラーニングなんてできるの?」新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言を受けて、壮大な社会実験場と化した教育現場。今回は、オンライン授業でアクティブラーニングを実践している方々をお呼びして、実践ノウハウをご発表いただきます。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-7/
講演1講師:本間 正人(京都芸術大学・副学長)
講演2講師:田原 真人(トオラス(旧・与贈工房)創業者)
講演3講師:阪井 和男(明治大学 法学部・教授)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年6月20日(土)13:00-15:00
テーマ1.ネットワーク授業と新しい大学
オンライン授業の実践から見えてきたこと
緊急事態宣言がなされて以降、全国の大学ではオンライン授業への全面的な切り替えが行われました。これはいわば教育のデジタルトランスフォーメーションという全国規模の社会実験が始まったことを意味しています。この前代未聞の巨大なデジタル渦(ボルテックス)に投げ込まれた私たちは、さまざまな軋轢や葛藤のなかでもがいている状況と言えるでしょう。
このデジタル渦の渦中にいる私たちは、今、何を見て、何を実践・経験し、何を感じているのでしょうか。このことを共有し、その意味を理解することから、新しい教育の息吹が生まれてくると期待されるのではないでしょうか。
このような観点から、継続的な観察と経験の共有が求められていると捉え、「オンライン授業の実践から見えてきたこと」を企画しました。
今回は、オンライン授業を受講する学生たちの生の声を聞き、実践する教員たちの苦闘の経験を共有する機会とします。
https://www.jmooc.jp/workshop2020-3/
講演1講師:見上 一幸(尚絅学院大学特任教授、日本ESD学会理事、宮城教育大学前学長 )
講演2講師:高見澤 秀幸(秀明大学 英語情報マネジメント学部准教授、情報コミュニケーション学会前会長)
講演3講師:宮原 俊之(帝京大学 高等教育開発センター主任・准教授/教育方法研究支援室室長)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年5月30日(土)13:30-16:00
テーマ1.ネットワーク授業と新しい大学
ネットワーク授業の隠れていた力を引き出す
新型コロナウイルス感染症の世界的拡散に対する教育継続の対策として、多くの大学でオンライン授業が一気呵成に導入されました。日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)ではこれまでオンライン授業を配信してきた実績があり、その状況の報告と今後の問題などを掘り起こし、これまで大学の授業に比べて、オンライン授業がどのような新しい教育の可能性をもたらすのかを考えることは重要です。
今回のワークショップは、オンライン授業による「学び」を如何に効果的に実現するかについて、実践的視点から継続的に議論するJMOOCワークショップのキックオフイベントとして、「オンライン授業の隠れていた力を引き出す」をテーマにして開催します。現在のJMOOCが提供している教育コンテンツなどの紹介も交えながら、今後の大学人の連携による新しいプログラムや講座について議論します。
https://www.jmooc.jp/20200526-1/
講演1講師:西山崇志(文部科学省高等教育局専門教育課企画官)
講演2講師:飯吉透(京都大学理事補・高等教育研究開発推進センターセンター長・教授)
パネリスト:飯吉透(京都大学理事補・高等教育研究開発推進センターセンター長・教授)、重田勝介(北海道大学情報基盤センター准教授/(一社)オープン教育研究所代表理事)、岸磨貴子(明治大学国際日本学部准教授)
モデレーター:朝日透(早稲田大学理工学術院教授・グローバル科学知融合研究所所長)
このワークショップを初めから観る
2020年度
2020年4月10日(金)13:30-15:40
プレイベント
新型コロナウイルス流行下での教育・研究の継続方法に関する報告会
現下の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、各大学において教育・研究の継続に向けた様々な対策、検討をできるだけ早く進め、できるだけ幅広い対応策を用意する必要があります。JMOOCでは、まだ手探りの状況の大学が多い中、多くの大学間での情報共有を行うためのWebシステム会議「新型コロナウイルス流行下での教育・研究の継続方法に関する報告会」を開催しました。
https://www.jmooc.jp/%e3%80%90%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%bb%e8%b3%87%e6%96%99%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%80%91%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%b5%81%e8%a1%8c%e4%b8%8b%e3%81%a7/
講演1講師:西山崇志(文部科学省高等教育局専門教育課 企画官)
講演2講師:佐波 孝彦(千葉工業大学 副学長 )
講演3講師:寺下 陽一(京都情報大学院大学 副学長)
講演4講師:足立 好弘(京都橘学園 法人事務局長)
このワークショップを初めから観る